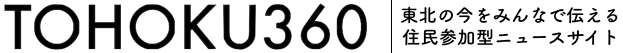【古山裕二通信員=岩手県雫石町】 岩手県雫石町で伝承されている「花饅頭」づくり。ひな祭りの日につくられる菓子で、雛人形に供えて女の子の健やかな成長を祈るそうです。その「花饅頭」に欠かせないのが、形づくりに用いる木型。実はこの木型、各家庭に代々受け継がれたものがあり、そこに彫られた模様も花だけではなく、さまざまな種類があるのです。
「もっと、ぎゅうっと押し込むように。そうしないと形が崩れやすくなるから」
用意された木型に、春を感じさせるピンク、黄、緑、白色の生地を詰めていく子どもたちへ、ベテラン指導者が声をかけます。詰め込んだ後は木型を逆さにし、トントンと軽く打ち出すと、さまざまな形の生地が飛び出てきます。「わぁっ」と子どもたちの歓声。
3月3日、雫石町の農業者トレーニングセンターで行われた「しずくいし食の伝承者養成講座」。この地域で伝承されてきた保存食やそば打ちなどの技術を学んだうえで、子どもたちへと伝えていくプログラムが2016年度より実施されています。この日は指導者役を務める受講者たちと、雫石町立西根小学校の児童や保護者ら約30名が参加。男の子たちの姿も見られました。

手にずっしりした感触のある木型は、雫石で生育している「朴(ほお)の木」を用いてつくられたものだとか。大工さんなど木を扱うのに長けた人が「彫り師」として、各集落での木型づくりを引き受けていたそうです。木型に彫られた模様は梅の花、葉、扇、たけのこなど、さまざま。桐山さんによると「各家庭で、つくりたい模様を彫り師に依頼していたらしい。いろんな形があるようです」とのこと。「たけのこの木型はきっと、子どもがすくすくと成長することを願ったものなんだろうね」